百年文庫90「怪」五味康祐 岡本綺堂 泉 鏡花

目次
「喪神」五味康祐
幻雲斎は豊臣秀次の側近召し使えを断り隠棲しました。その幻雲斎に挑みに現れたのが奉納試合で幻雲斎の敗れた稲葉四郎利之の子松前哲郎太重春でした。幻雲斎は哲郎太の右耳をかすめ取り命を助け、「何時なりと隙あらば挑むがよい」と一緒に暮らすように勧めました。哲郎太は幻雲斎の養女「ゆき」と夫婦となり三人で暮らしました。修行を始めて八年がたったとき、幻雲斎は哲郎太に山を下りるよう勧めました。哲郎太が別離の会釈をし歩き出したとき幻雲斎の仕込み杖の刃が閃きました。しかし、血を噴いたのは幻雲斎でした。妖剣の奥義が伝わった瞬間が劇的に描かれています。
「兜」岡本綺堂
大正12年の震災に遭った邦原家でただ一つ助かった「兜」の話。ひとりの女が避難先にこの兜を届けてくれました。
兜が邦原家に伝わった由来は60余年前の江戸末期までさかのぼります。所持する者が相次いで辻斬に遭ったといういわく付きの兜を引き取りましたが、間もなくその兜が盗難に遭い行方不明になってしまいます。明治元年、邦原家の主人となった勘次郎は維新の混乱のなか道端で兜を見付けました。そして官軍から身を隠すために駆けこんだ家をあとにするとき、その家の女に兜を譲りました。後にその女は子供とともに自害し、兜は近所の者が古道具屋へ売り払いました。明治22年、勘次郎は夜店の古道具屋でその兜を見付けます。
と、因縁めいた兜ですが、兜を届けた女も兜を譲り受けた女も左の眼の下に小さい痣があったというのですから、少しぞっとしてしまいます。
「眉かくしの霊」泉 鏡花
木曽路奈良井宿が舞台。代官婆と呼ばれる庄屋の婆さんの息子は東京で学士をしています。代官婆はその息子の嫁を連れて村で暮らしていました。そこへ息子の友達の画師が訪ねて来ます。画師は芸妓お艶と馴染となった末に妻と不仲となり東京から逃げてきたのでした。ところが画師は学士の嫁と姦通騒ぎを起こし代官婆に吊し上げられてしまうのです。その事件の後に奈良井宿を訪ねてきたのが画師の馴染みであるお艶でした。お艶は代官婆を訪ねて行きましたが、元奉公人の石松に撃たれてしまうのでした。お艶が泊まった旅館に霊が出ます。艶めかしく幻想的な物語でした。
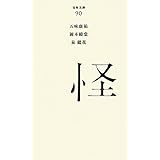 |
中古価格 |
![]()