百年文庫92「泪」深沢七郎 島尾ミホ 色川武大

目次
「おくま噓歌」深沢七郎
おくまは、畑を耕し鶏を育てながら、息子夫婦と5人の孫たちと暮らしていました。バスを二つ乗り継いだところに住む娘は4人の子育てに追われており、時々それを手伝いに出かけていました。バスに乗るのは疲れるし赤ん坊を長く背負うのも辛かったのですが、娘を少しでも休ませてやりたくて「慣れているから」と嘘を言いました。家に帰って、「疲れつら」と言われても「なに、いっさら」と嘘を言いました。孫が東京から友達を連れてきたとき、自分の姿をみせたら孫が恥ずかしいだろうと「グアイが悪い」と嘘を言って物置小屋に隠れていました。おくまは死ぬ時も枕元で「よくなって」と泣く息子夫婦に「ああ、よくなるさよオ」と嘘を言いました。家族のために働き続け亡くなっていく母親の姿が胸を打ちます。
「洗骨」島尾ミホ
「洗骨」とは一度土葬した死者の骨を水で洗って再度埋葬することで、日本では南西諸島にこの風習があったそうです。奄美群島では「改葬」と称していて、作中にもこの言葉が出てきます。「死後3年もしくは7年とか13年経過した人たちを改葬(洗骨)し、親類縁者で宴をもち霊を慰め重荷をおろした喜びをみんなでわかちあう」とあります。歌に合わせて亡き人の霊と一緒に老若男女が踊って生前の姿を見る。亡き人に対する思いを率直に表現する能動的な風習と感じました。
「連笑」色川武大
競輪、競馬、麻雀を生活の一部としながら小説を書いている主人公「私」とその弟の物語です。子供の頃、弟はいつも私の後をついて歩きました。殴れば泣いてしまいます。そのくせどこまでも後をついてくる不思議な関係は、大人になっても続いているように見えます。「これじゃアな」「どうにも、しょうがないね」と、二人には二人だけの笑いがありました。弟は放埓な私の唯一の理解者でした。言葉には出来ませんが確かにそこにある肉親の情が感じられました。
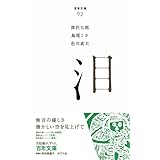 |
中古価格 |
![]()