百年文庫97「惜」宇野浩二 松永延造 洲之内 徹

目次
「枯木のある風景」宇野浩二
「枯木のある風景」とは主人公古泉圭造の絶筆の一つである油絵で、八田弥作がこの絵について次のように説明しています。
「画面の下半分が枯野の明き地」
「画面の下四分の一ぐらいを占めて大きな枯木の丸太5,6本が横倒しに転がっている」
「画面の上半分は冬らしい冷たい色の空が占めている」
「その空と枯野の間、つまり地平線は、バラック建ての平家と低い丘とで仕切られている」
「平家の前の往来と思えるところに高圧線の鉄骨の電柱が立って冬空を二分している」
「電柱の上の方と下の方に5,6本ずつ電線が張られ……」
「……その上の方の電線の一番上の線に、黒い烏のようなものが止まっている……」
「……それが、人間やないか……」
この作品は、画家の小出楢重がモデルになっているというので、ネットで調べてみると、なんとその絵は実在していて、確かに八田が説明したとおりの絵でした。芸術家が遺した絵に込められた思いを小説という形で描いた作品でした。
「ラ氏の笛」松永延造
「ラ氏」とはインド人の貿易商ラオチャンド氏のことです。ラ氏は「私」が勤める病院に入院していました。おそらく結核なのでしょう、高熱と吐血で体は衰弱していきました。彼は巧みな笛吹でした。一人の女性が金を借りたいがために彼に近づいてきましたが、彼が笛を吹くように差し出すと女性はそれを拒みました。ある男性はラ氏が差し出した笛を吹こうとしましたがラ氏はそれを制しました。「いつも不幸でもって、幸福を買った」と言っていたラ氏が、死という最も大きな不幸で買い取った幸福とは何なのか、「私」はその問いに答えることが出来ません。病による孤独に圧迫されるような小説でした。
「赤まんま忌」洲之内 徹
19歳の三男が交通事故に遭ったという知らせを受け、その後葬儀を終えるまでの様子が過去の出来事とともに淡々と綴られています。作者は東京で画廊を営んでおり三男は実家のある京都に帰省中でした。折に触れて思い出される三男や家族とのやりとり。つい数日前までそこにあった何気ない日常。子供と打ち解けて暮らした2,3日。「……その稚いところに、この赤まんまの花はなんとなくふさわしいような気がした」という思いの披瀝。同じように親子の時期を過ごしてきた者として、その飾りのない言葉が胸に沁みて来ます。
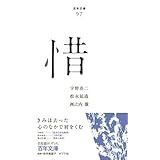 |
中古価格 |
![]()